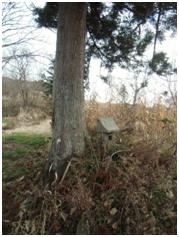活性化委員会 西河原地籍の「割り上げ」勉強会
投稿日:2016.03.012月15日(月)活性化委員会プロジェクトチーム「割り上げ班」の勉強会が行われました。
七二会は論地泥岩層に属する急傾斜地で、県下随一の地滑り地域とも言われています。昭和26年に地質学者の八木貞助氏の調査によると、地区全体の26.8%で432ha(17箇所)が地滑り地帯で、この率は県下一と言われていました。
しかも、地区の生活舞台の標高600m前後を地滑り帯が横切っており、古くから地滑り対策事業が盛んに行われて来ました。
五十平区と平出区の間の西河原地籍は、その中でも、古来より地滑りが多発する地域であり、耕地を守るため、全国でも稀な「割り上げ制度」を実施して、各耕作者の面積と収穫の平均を図って来たと言われています。
何時の時代から始まったのか定かではありませんが、古文書によると、開田は宝暦8年(1758年)以前というから260年近い歴史があると思われます。
【現地調査前の勉強会】
【現地調査】
谷原集落の北側にある動かない二つの大岩に不動天を求め、一方の岩の頂上に掘られた穴の中に磁石を据え、そこから子(北)の方角(七二会村史では北西の方角)に14間3尺の線を引き、これが五十平区と平出区の境界の基準点となり、そこから横線(西)縦線(南)との交点を求め、この点を結んでいく事により境界線を復元したと言われています。その境界線が大境となり、その後、個々の農地の区割りを三角法により実施したと言われています。
【不動点の一つ石祠】
この特殊な「割り上げ制度」は、昭和28年を最後に中止となりましたが、今回、活性化委員会プロジェクトチームでは、全国でも稀な方法で「割り上げ」した先人の知恵を再現したいとの事から活動を開始しました。素人集団ではハードルが高いので、中島誠至建築設計事務所の中島先生にもメンバーに加わっていただき、故早川早夫氏が五十平公民館報「いせみや」に掲載された文献を基に再現作業を実施しています。
次の記事
七二会の魅力を紹介してきました♪
前の記事
ご協力ありがとうございます!なにあいドットコム半年間毎日更新できています